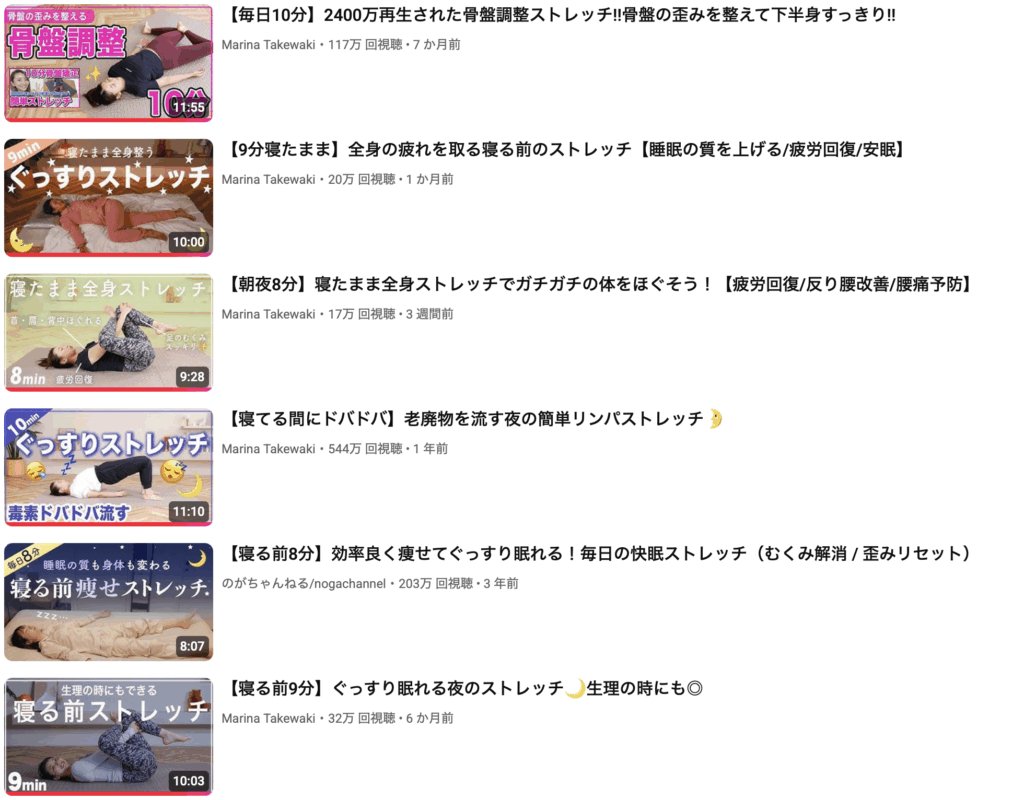前回、視力について書いたのは2008年のこと、それから17年が経ち、私も54歳になリました。いま、メガネを取り巻く環境も自分の視力も少しずつ変化している。今回は、その変化の中であらためて感じたこと、そして新しく試していることを記してみたい。
私はメガネを使い分けている
今までは①から③の三種類で生活をしていました。一つ目は週末にバイクでワインディングをスポーツライディングするときに使うもの。コンセプトは5から10m程度の距離感で路面にある枝や石をしっかりと見極めてフロントタイヤのラインを避けること、また普段はしないけれど夜間走った時に信号がボヤけて見にくくならないためのもの。二つ目はプロジェクターを使ったリアル会議や展示会のパネルを読むときに最低限読めるもの、あとはPCで作業をする時のメガネ。そしてこのPC用を普段使いとして愛用しています。そして今回、四つ目として本を読むためのメガネを新調しました。
各メガネの度数比較表
① バイクスポーツライディング用 : 遠方視力重視。高速走行や遠景観察に最適。
② プロジェクターやパネル会議用 : 日常・屋内向き。会議室やプロジェクター距離に適合。
③ ノートPC用(日常用) : ノートPCや中距離用途。普段使いも兼ねる。焦点距離約50〜60cm。
④ 本・スマホ用 : 近距離・読書・iPhone用。焦点距離30〜40cm。
| 用途 | PD | R SPH | L SPH | R CYL | L CYL | AXIS | 視力 | 購入 | 焦点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 63.0 | -4.00 | -4.25 | -1.00 | -0.75 | 10 / 15 | 1.2 R>L | 2021 | 5〜10m |
| ② | 63.0 | -3.50 | -3.75 | -1.00 | -0.75 | 10 / 15 | 0.8 R>L | 2021 | 2〜4m |
| ③ | 61.0 | -2.50 | -2.50 | -1.25 | -1.00 | 10 / 15 | 記載 なし | 2025 新調 | 約50〜70cm |
| ④ | 61.0 | -2.00 | -2.00 | -1.25 | -1.00 | 10 / 15 | 記載 なし | 2025 新調 | 約30〜40cm |
本用のメガネを追加した理由
2021年に三種類のメガネをそろえた当時、私はちょうど50歳だった。CBR600RRでのワインディング走行を再開した年でもある。走りの中で気づいたのは、コーナーの進入時、わずかな路面の変化が見えにくくなっていることだった。小石一つが見えないだけでライン取りは大きく変わる。これを補うために遠方視重視のライディング用を作り、同時に仕事ではリモート会議や長時間のPC作業が増えたことから、肩こりと眼精疲労対策としてPC用メガネを作った。あれから4年。日常の中でもうひとつ大きな変化が現れた。iPhoneの文字が見えづらいのだ。そう、ついに老眼の兆候が訪れた。メガネを外さないとニュースが読めない。しかも本を読むと、文庫本の小さな文字に焦点が合いにくく、疲れた時には霞むようにも感じる。人間の目は、もともとある程度の距離幅に自動的にピントを合わせる仕組みを持っているが、その調整幅が加齢とともに狭くなっていくのだろう。
本・スマホなど近距離での読書用を追加
そこで今回、本やスマートフォンの近距離専用として最も弱い度数(SPH -2.00、PD61.0)のメガネを新調した。焦点距離は30〜40cm。文字や写真が自然な姿勢のままはっきりと見えるように設計した結果、遠くはぼやけるものの近距離のコントラストが驚くほど高くなり、テキストを読む集中力が増した。文字がくっきりと見えるというのは単に情報が読み取れるということではなく、思考のノイズが減り、文章の世界に深く入り込める感覚をもたらす。これは少し矛盾するようだが、明瞭さの中にリラックスがある、という不思議なバランスである。
感想
新しいメガネを使ってみて感じたのは、「本が読める」という単純な喜びだ。年齢とともに読書の体力が落ちたと思っていたが、テキストを楽に認識できるだけで、以前よりも長く読めるようになった。少しの“楽”が、習慣を支える大きな要素になる。読む時間が少し伸びるだけで、知識や発想が積み重なっていく。新しいことに挑戦する意欲もまた、視界の明るさとともに蘇ってくる。
そして同時に、PC用メガネ(③)も同じ仕様で作り直してみた。すると驚くほど視界がクリアになった。目に入る光が明るく、画面の輪郭がよりくっきり見える。調べてみると、これは理にかなっているらしい。近年のレンズは素材やコーティングの透過率が向上し、光の散乱が減ってコントラストが高まっている。古いレンズは紫外線や皮脂の影響でわずかに黄変し、微細な傷が光を乱反射させる。つまり、樹脂レンズにも寿命があるということだ。同じ度数でも、新しいレンズは明らかに“抜け”が違う。
メガネは単なる視力補助具ではなく、自分の世界をどの距離で、どんな明るさで見たいかを選ぶツールになったと感じている。焦点の合う距離を増やすことは、見える世界を広げることそのものだ。定期的に作り替えることで、光を正しく通す“視界の質”を保てるなら、それは十分に価値のある投資だと思う。新しいメガネをかけるたび、見慣れた風景の輪郭が少しだけ鮮やかに感じられる。ピントが合う距離が増えるほど、人生もまた、少しピントが合っていく。
やはり樹脂レンズって、消費期限的なもの、劣化も存在する。この劣化は視界だけでなく人生の明るさにもつながる。昔と違ってメガネも安くなったので、定期的に交換していきたいと思います!!